初代神武天皇、
東北平定した
10代崇神天皇、
「俺と旦那、どっちが好き?」と兄に聞かれて兄を選んだお妃を
ずっと一途に愛した
11代垂仁天皇、
80人ものお妃を持った
12代景行天皇、
(ヤマトタケルの父)
国と国に境界線を敷き、国の代表者を決めて
中央集権国家のひな型を作った
13代成務天皇。
成務天皇の跡継ぎがいないため、
兄弟であるヤマトタケルの血統に移り―…
ヤマトタケルの子である
14代仲哀天皇が後を継ぎ―…
仲哀天皇はヤマトタケルの子、という重荷が有りましたが、
それを丸々補える程の勇ましい皇后がいました。(
神功皇后)
そのおふたりの間に生まれた
15代応神天皇、
応神天皇は母親と違って穏やかでのんびりした性格でした。
母親が成し遂げた三韓征伐でしたが、
その三韓、即ち朝鮮と、その奥の漢、呉とも交易を重ね、
応神天皇の御代は
争い事もなく平和な御世になりました。
その後は
(穏やかでのんびりとした性格から、と紐付けると覚えやすいです)
末子の優しいウジノワキを跡継ぎに指名しますが、
応神天皇が崩御した後、
跡継ぎに対し納得いかない長子のオオヤマモリが
ウジノワキを攻めますが、返り討ちに遭います。
兄の反逆、そしてそれによる死を見て
末子の自分が跡を継ぐのは国の混乱を招くと判断し、
ウジノワキは中間子の
大雀命に即位を願い出ます。
大雀命は父親からウジノワキのことを強く頼まれているので
それを断ります。
が、そうこうしているうちに、ウジノワキは薨去してしまいます。
死因はハッキリしていませんが、深い心因性のものと思われます。
そして大雀命が
16代仁徳天皇として即位します。
ここまでが、「父→子」が基本だった皇位継承となります。
仁徳天皇の、次の世代からは
「兄→弟」という皇位継承が前例として定着して行きます。
仁徳天皇と皇后には4柱の皇子がおり、
長男→三男→四男、の順で即位しました。
17代履中天皇
18代反正天皇
19代允恭天皇
・・・
・・・
さて、この
19代允恭天皇にはとても出来の良い長男がおりました。
が、やはり古事記の不可思議なルールの通りなのか、『長男』には問題がありました。
何と、自分の実の妹と相思相愛の仲になってしまったのです。
異母兄弟ではなく、正真正銘、実の兄と妹、という間柄です。
たいてい、
大河物語だとか、大きな叙事詩(歴史ものを語った詩)などは
『戦記もの(英雄譚)』、というものと
『恋愛もの』という...2大カテゴリーがあるように思われます。
壮大な物語や伝記伝承は、上記のふたつのものが
人々に注目されやすいのか...残されやすい傾向にあります。
例に漏れず、「古事記」ででも、
戦記もの(英雄譚)としてヤマトタケルの伝説が残されており、
同じく人々から注目されやすい(求められやすい)要素である
「恋愛もの」は残るべくして残った、と言えるのかもしれません。
しかし「恋愛」となると、
これがもし、天皇以外の存在が その物語の主人公になると、
天皇以上に注目を集めて目立ち過ぎてしまうことになるし、
かと言って天皇とお妃の恋物語...と言っても
その立場上、多くの女性と結婚をし、子供をもうけなければならない『天皇』と言う特性がある以上
それは生じづらい、残りづらい、と言えるのかもしれません。
だから、皇太子と、実の妹という立場の相手が丁度「恋愛もの」としての登場人物に合った、
という可能性があります。
悲恋である以上、物語として充分成立しますし、
皇太子の恋の相手が一般人だと、その物語の流れとして
「皇族と恋が出来ない一般人可哀想」という雰囲気になってしまいます。
・・・
さて、
允恭天皇が崩御された後、
当然の如く、妹と愛し合っている
木梨之軽王は
家来からも国民からも非難されました。
木梨之軽王の弟である、
穴穂御子に人心は傾き
木梨之軽王は島流しにされました。
妹である
衣通郎女も謹慎させられました。
衣通郎女、とは通り名で、
その美しさが袖を通して光り輝いているためにこう呼ばれていました。
しかし我慢出来ずに、妹は謹慎中の館から抜け出し、
兄のいる島に会いに行ってしまいました。
淡々と文字だけ書いても相当にドラマチックなのですが、
実際はもっともっと激情的であり、ロマンチックです。
この兄妹の交わした和歌で、
後々の和歌の恋愛歌においての枕言葉や決まりや恋愛歌の種類の名称が生まれました。
周りの人間たちも、ふたり↑の兄弟である穴穂御子も傍にいるのに、
堂々と和歌で愛を語らい、
周りのドン引きしている圧力が全く通じない有様でした。
兄弟の穴穂御子にとっては、
実兄と実妹が、共にこんなことになってしんどいことこの上なく、
そして天皇の器ではない兄の代わりに天皇に即位しなければならず、
一番辛かったのではと思われます。
上記の「周りの人間がいる前で堂々と~」というくだりは
木梨之軽王が島流しにされる直前の場面です。
「恋をしてしまったのは、
恐らく本能的なものだからしょうがないとして
そのこと自体はどうしようもないものだから...
その想いは私は反対していない。
でも、何故それを止めようとしないのか、
抑えようとしないのか
兄上と衣通郎女はお互いの恋を自ら価値を下げている」
と穴穂御子は言ったかどうかは定かではありませんが、
兄が島流しになった島に行き、兄と再会した妹は
そのまま美しい恋愛歌をたくさん詠み合いました
君が往き 日長くなりぬ
やまたづの 迎えを行かむ
待つには 待たじ
あなたが旅立ってしまってから 随分と長いこと経ってしまいました
迎えに行きます
待っていられるものですか
(衣通郎女)
隠り処の 泊瀬の山の
大峰には 幡張り立て
さ小峰には 幡張り立て
大小よし 仲定める
思ひ妻あはれ
泊瀬の高い山にも低い山にも 葬式の旗を立てよう
それほどに運命を共にしようとした
我が妻よ、愛おしい
(木梨之軽王)
ふたりはそのまま心中してしまいました......
穴穂御子の悲しみはいかばかりだったでしょうか。
実際は疲れの方が多かったかもしれません。
・・・
穴穂御子は
20代安康天皇として即位します。
漢風諡号の「安康」はそのまま、
穴穂御子の願いを表しているもののように思います。
ここまでの系図の説明
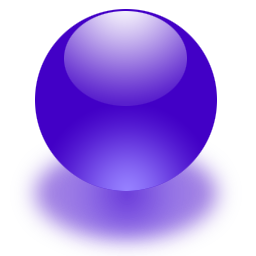 (これまでのあらまし)
(これまでのあらまし)