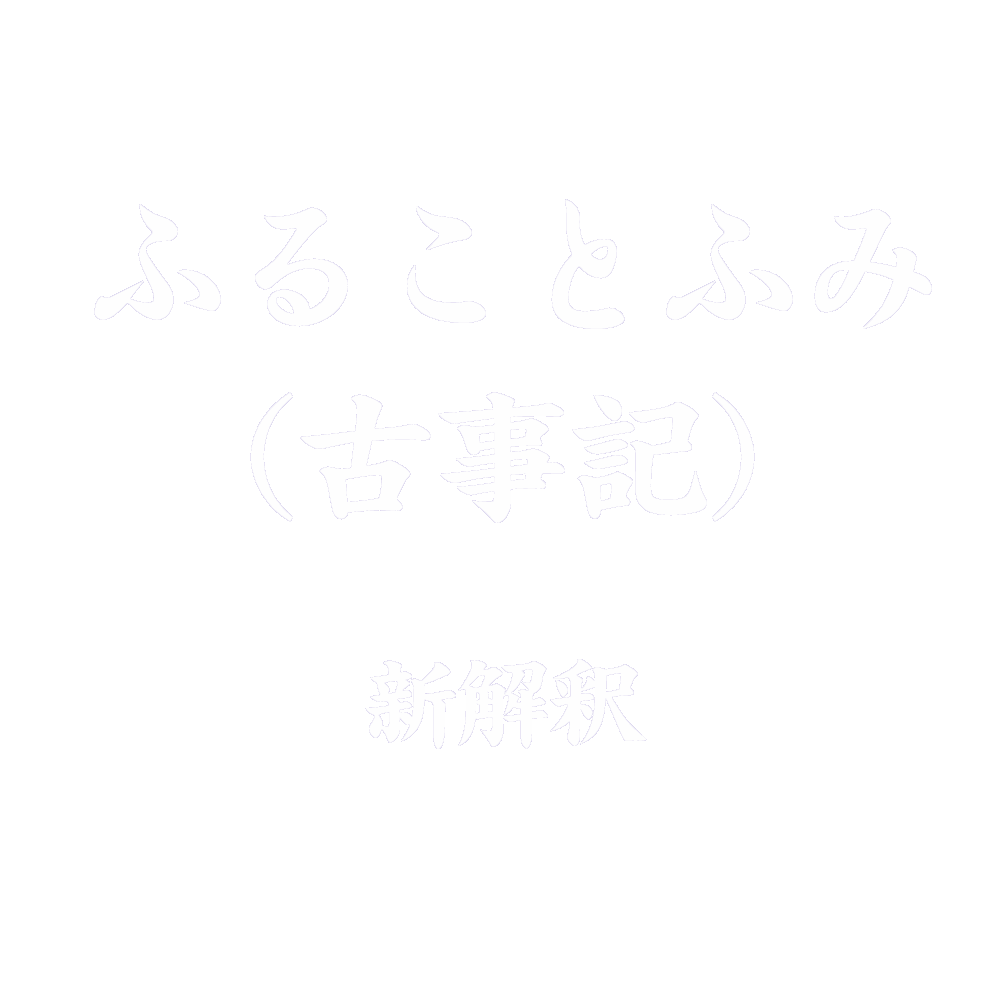第9節:わびさび
第1話:わびさび
遺しておくものは遺さなければならない。
最後の理性か―・・・。
国を勢い付かせたけれど、
でも同時に、明るく燃やし過ぎて、
勢いは付いたけど、、
気付いたら全焼していた。
そんな某一族。
滅ぼされる直前に、色んなものを燃やしたのだけれど、
蝦夷(えみし)は、最後の最後の理性で、「国の大事な歴史」そういうものは
燃やさずに土に埋めた。
しかし、表向きは『火事で焼けちゃいました』と敵に心理的ダメージを与えて、
最後の意地悪をした。
最後の良心は
これだけは守らないといけない、という理性が働いたことで、
最後の最後までくすぶっていた邪な気持ちは
「とりあえずダメージ与えてやるもん」・・・
日本人としての良の部分が最後に出たけれど、
堕ちた?日本人として最後まで邪で終わった、というのが
わさび
飛鳥時代と言えば聖徳太子だが、
他にも推古天皇や蘇我馬子、蝦夷、入鹿などがいる。
そこで出て来る、乙巳の変(いっしのへん)。
中大兄皇子に蝦夷、入鹿が滅ぼされ―・・・
と続く。
その、
中大兄皇子の弟、天武天皇の命により日本最古の公的歴史書の編纂が命じられた訳だが―
それよりも前に「公的」と名の付くほど力のあるものではなかったが、
歴史書は存在した。
歴史書は存在したのである!
天武天皇が編纂を命じた『古事記』が出来るずっと前から!
それを、蝦夷・入鹿親子が、滅ぼされる前に全部燃やしてしまったのだ。
正確に言えば、その時はすでに入鹿は中大兄皇子に命を奪われ、
幽霊になっていたので
燃やしたのは蝦夷だが。
(蘇我氏の系図)
蘇我馬子(父)→蘇我蝦夷(子)→蘇我入鹿(孫)
勢いのある、華やかなものは、元々そういう、盛んな気質を持つ者がやるべきで、
むしろ堅実だったり地味なものだったりわびさびを好む者がするべきではなかった。
わび(侘び)=貧相、不足なものの中に、精神的な美しさを見出そうとする気持ち。
さび(寂び)=古いものや朽ちた「もの」そのものに物理的な美しさを見出そうとする気持ち。
一度だけ、小さい頃の顔を至近距離で見たことがあった。
蝦夷は、中大兄皇子がとても小さい頃に、こけそうになっていてすごく危なかったとか
何かそういう理由で、庇ったか何かで顔を見てしまったことがあった。
振り返ったその顔が、
「昔 蝦夷さんがこんな気持ちだった、と誰か書いておいて欲しい」
と思わせる顔だった。
虚を突くとはこんなことを?
ひと目惚れの感覚に似ている。
別にひと目惚れした訳ではないが、とにかく「虚を突かれた」感じであった。
ちょっとあなた!と声を掛けようとしたら
漫画キャラが出て来たような、、こう、、虚を突かれた感じである。
だからと言って、惹かれたとか良いと思った悪いと思った
これこれこう思った、というオチはひとっつもないのだが
とにかく感覚だけは覚えていた。
蝦夷も死の直前になって、あの感覚だけでいいや。と思った。
目で物を見る感覚。
具体的な心の感覚。
もうあれを知ることが出来たからいいか、もう生きる使命が終わった。
本来なら、それに続くステップ(好意を抱くとか嫌悪感を抱くとか、興味を持つとか)に
繋がるのだが、
それがないまま亡くなった。
第7章:その他「第9節:わびさび ー 第1話:わびさび」
第9節:完
BACK「第8節:阿閇皇女(あへのひめみこ)」
NEXT「第10節:相撲」